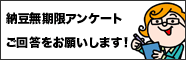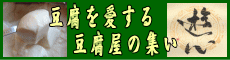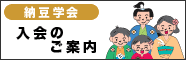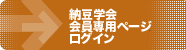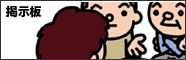最終更新日 平成15年2月16日
平成12年4月のある日、新潟県上越市(直江津)の市(いち)にでかけてきました。
実は私は上越市の生まれなので、祖母と一緒に懐かしい市にでかけた次第です。
上越市ですが、「武将でいえば上杉謙信」といった方が分かりやすい?かも知れません。
ちなみに日本史の謎として、「上杉謙信不犯の謎」というものがあります。
(不犯は「ふぼん」と読みます)
謙信が生涯、女性と人類の根元的行為をしなかったという謎なのですが、学生時代、この謎に大変興味を覚えて、『謙信はチェリーボーイだったか?』という論文を書いたことがあります。思春期だったからでしょう、こうゆうネタには、熱が入ったものです。
この前見つけた、三谷茉沙夫著『淫の日本史』桜桃書房という本には、日本史にでてくる人物のこういったネタが詰まっていて、「大人」の方には面白いのではないでしょうか。
話が飛びましたので、元に戻します。
市は大変活気があふ○○、売り手の声が高々と
「・・・・・・」
「・・・・・・」
なく、大変地味な市でした。
土地の気質の違いでしょうか。能登半島は輪島の朝市に行ったときには、
「おに〜ぃ〜ちゃん、買(こ)うっててぇ」
とアクティブな売り手が多かったのですが、こちらは寡黙かつパッシブで、なかには舟を漕いで居眠りしているおばあさんもいます。
そんな中、色々と大豆関係を探すと、自分の畑でとれたらしき大豆を売るおばあさんがいらっしゃたので、地元での大豆作りについて色々と聞いてみました。
「すいません、私、柏崎に住んでいるんですが、どんな大豆を育てたらいいか、教えて頂けますでしょうか?」
「そうだにゃあ、柏崎だとぉぉ・・こことおんなじ豆でいいんじゃないかねぇ」
というお話から、茶豆は難しいとお話などまでして、おばあさんに色々と教えて頂いたのち、味噌用大豆5袋、緑豆1袋を購入しました。1袋には、かなり年季の入ったマスで1杯約700gが入り、お値段は250円(税なし)でした。
早速、自宅に帰り、緑豆を関越自動車道谷川岳SAで汲んできた、谷川岳の水に一晩浸しました。
本当は、ここで豆の選定をした方が美味しい納豆ができるのですが、フランス人の血をひく私としては(ウソ)「自由・平等・博愛」というフランス革命の精神であえて選定はせず、すべてを受け入れ、フランスの香りを醸しだしてみました・・・香りなんかでません、もちろんウソです。
翌日、圧力鍋で強火12分、弱火5分、むらし5分で、ふっくらと茹であがり、タッパーに入れたところで、すかさず成瀬研究所の納豆菌を霧吹きでプシュプシュ。100円ショップで購入した霧吹きが大活躍です。
タッパーを毛布でくるみ、こたつで一晩寝かせて翌日に完成!
表面にうっすらと白い膜をはった、なんとも美味しそうな緑豆納豆ができあがりました。

(クリックすると大きな画像が表示されます)
たまり醤油にわさびを溶いて、刺身のようにチョイとつけて、口に頬張ると、大豆の甘みが広がり、ある程度の広がりを見せたら、わさび醤油が引き締めています。
当然、ビールもグビグビ入っていきます。
あまりに美味しくできたので、これから3年ほど冷蔵庫内で保存し、
「長期熟成 緑豆納豆 ローヤル3年」
として、また3年後に楽しみたいと思います。
地元の大豆、地元の美味しい水での納豆造りは、地元の人とのふれあいもできて、楽しくもあり、もちろん美味しくもあります。
皆さんも、お近くで市などある際はお出かけになってみてはいかがでしょうか。
*今回の緑豆納豆は、3年後のオフ会、もしくは納豆学会でおめでたいことがあったときに、希望される方とともに試食してみたいと思います。
冷蔵庫にて、空気穴(直径5mm程度)を空けた使い捨て弁当容器で熟成中です。
4月5日を1日として、その後の模様(画像)をアップします。
・平成12年4月19日(14日間後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
・平成12年6月4日(2ヵ月後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
かなりチロシンが多くなってきて、目を刺すようなアンモニア臭がします。
・平成12年7月10日(3ヵ月後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
さらにチロシンが多くなり、水分も無くなってきました。
・平成12年10月10日(半年後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
チロシンで豆覆われてきました。
・平成13年6月9日(14ヶ月後)
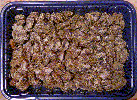
(クリックすると大きな画像が表示されます)
いよいよ1年を超えて、ほとんど水分はなく、アミノ酸の結晶となってきました。
・平成13年9月23日(17ヶ月後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
アミノ酸の結晶が隣の結晶とくっつきはじめました。
・平成14年2月12日(22ヶ月後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
目に刺すような臭いが”こなれて”きました。
・平成14年8月30日(28ヶ月後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
さらに乾燥が進み、白い塊になってきました。
・平成15年2月15日(34ヶ月後)

(クリックすると大きな画像が表示されます)
「助さん、格さん、もういいでしょう」の20時37分状態。
*「緑豆」という呼び方について、会員のカエル子さんから以下のようなご質問をいただきました。
『「緑豆」って、種皮の緑色の大豆のことですよね?私は今まで、
「青豆−あおまめ」と呼んでいました。
「緑豆」だと、「りょくとう」と読んでしまいそうなので。
私は北海道に住んでいるのですが、
他の地域では、「緑豆」と呼ぶのが一般的なのでしょうか?
どなたか、教えてください。』
このご質問に対し、私は以下のようにお答えしました。
緑豆という呼び名ですが、種皮の色の分類では黄大豆、青大豆、黒大豆と分類するので、「緑豆(リョクトウもしくはミドリマメ、リョクズ)」は呼称で、分類上は青大豆とするのが一般的です。
江戸時代での分類では、「万米(マメ)」(黄、黄白、青)と「久呂万米(クロマメ)」(淡紫色、黒褐色)の2種類で、万米は味噌に使い、久呂万米は薬として重宝されたそうです。
*おばあさんは「ミドリマメ」と呼んでおりました。
現在、青大豆に分類される品種でも「早生緑」、「秋試緑1号」、「秋試緑2号」というものがありますし、もちろん「青」の文字が入った「青目大豆」という品種もあります。
結局のところ、「緑色のことを青と言う」ことから来ていると思われます。
カエル子さんの「カエル」も、緑色なのに「アオガエル」と呼ぶのと通じるものがあるような気がします。ゲロゲーロ。
ちなみに、緑豆(八重成とも言われます)の歴史は大変古く、福井県三方町の鳥浜遺跡から緑豆が見つかっていますので、縄文時代には栽培されていたようです。
また、中華料理で使う春雨は、ビーズのように小さい品種の方の緑豆(リョクトウ)で作ります。
いま売られている春雨のほとんどは手がかからないジャガイモやサツマイモなどの澱粉ですが、あえて「緑豆(リョクトウ)春雨」と明記してあるものが緑豆(リョクトウ)で作った本物の春雨です。
中華料理などを食べに行った際に、春雨をひとすすりして、店主を呼びつけ
「おい、主。この春雨は緑豆(リョクトウ)だな」
「は、はい、そうですが・・・」
「フッフッフッ、今後、一層の精進をせい!」
海原雄山『美味しんぼ』風
といった場合にお使い?頂けます。
 その他のトピックスに戻る。
その他のトピックスに戻る。

トップへ戻る。

ご意見、ご要望はこちらまでお願い致します。
![]()
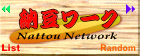
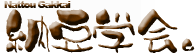
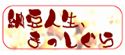






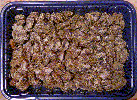




 その他のトピックスに戻る。
その他のトピックスに戻る。